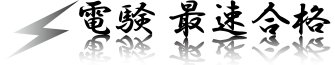電界と電位・ガウスの法則
静電気の単元は似たような言葉がたくさん出てきてややこしいですよね。電荷とか電位とか電気力線とか電界とか・・・。言葉で覚えるのではなく一つ一つどういったものなのかイメージして覚えるとよいかと思います。
電界
電界とはある場所に電荷をおいたときに受けるクーロン力の影響の大きさを表したもので、単位は[N/C]もしくは[V/m]を使います。
電荷量Q1[C]の電荷からr[m]離れた点における電界E[N/C]は

電位
電位とは、クーロン力の影響を受けない無限に離れた場所を基準(0V)として、その場所から1[C]の電荷をある場所に移動するのに要するエネルギーのことです。
例えば、下図のようにクーロン力を受けない無限に遠いところに1[C]の電荷があったとします。

この電荷が+Q[C]の半径r[m]の地点へ向かおうとすると、距離が近づくにつれて、クーロン力が大きくなっていきます。それに逆らうためにはエネルギーが必要です。

そうして、エネルギーをたくさん使用してようやくたどり着いた+1[C]の電荷はエネルギーを持っています。このエネルギーが電位というわけです。

身近な例でいうと、地面にある物体を高い場所まで持ち上げると、その物体は位置エネルギーを得ますよね。それと全く同じ理屈です。
このときの電位V[V]は
で表すことができます。
ガウスの法則
ガウスの法則の説明の前に電気力線と電束の話を先にします。
電気力線は、クーロン力という目に見えない力の様子を視覚的に分かりやすく表現した線のことで、その電気力線を何本か束にしたものを電束といいます。
分かりやすくするために本来ありえない数字を使っていますが、下図のようなイメージです。

まず、1[C]の電荷から1[C]の電束が出ます。次に電束を誘電率で割ったものが電気力線になります。なので、電荷量が決まると電束は決まりますが、電気力線は誘電率によって変わりますね。
さてさて、このときの電気力線の規則性に関する法則がガウスの法則になります。
覚えるべき法則は以下の6つです。
1.電気力線は正の電荷から出て、負の電荷に入る。
2.電気力線は途中で分岐したり、他の電気力線と交わらない。
3.任意の点における電気力線の密度は、その点の電界の強さを表す。
4.任意の点における電界の向きは電気力線の接線の向きと一致する。
5.同じ向きの電気力線同士は反発し合う。
6.任意の閉曲面から外に出る電気力線の数は閉曲面内の電荷の総量に比例する。
はい、一応まとめましたが、こんなの図の方が100%覚えやすいので下図のようにまとめました。

この6つの法則も電験3種の試験問題で出題された実績があるので、必ず覚えておきましょう。
自分で作って自分で言うのもアレですが、図の方が100%分かりやすいですよね。
でも、市販のテキストでこういった図を載せている参考書は今までにほとんど見たことありません・・・。まぁともかくイメージが大事なのでしっかりと図を見て一つ一つ丁寧に理解していきましょう。